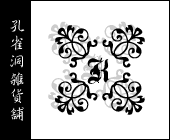
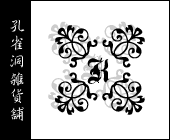

先週の土曜日、数ヶ月振りに骨董市へと行って参りました。
最後に足を運んだのは秋物の上着を着ていた記憶があるので・・・昨年のこと?
目当ては万華鏡の材料に使う時計の部品や色硝子だったのですが、めぼしいものはなし。
硝子製品は数年で随分と値が上がりましたね。・・・。
陶磁器専門のお店の中で、日常使い用に小皿を購入。小鉢というには浅く、小皿というには深い、ちょっと珍しい深さで使い勝手がよさそう。昭和48年のデッドストック品。
同じお店で展示のディスプレイ用にエスプレッソ用の小さなカップも購入、こちらは昭和30年頃、欧米輸出用のデッドストック、縁の部分は花弁型、胴の部分は緩やかに八角形、持ち手の部分はくるりと蔓のような曲線でとても愛らしいのです。
それから洋物家具を取り扱うお店で19世紀末の真鍮装飾具を入手。こちらは標本箱に使う予定。
一巡りしてから近くの日本茶喫茶でお茶していたらお友達にばったり、一年振りくらいでしょうか。嬉しい偶然。
kana wrote : 12:33 | comment (0)
恵比寿の週末雑貨店、atelier drop aroundさんの夏休み企画、寺子屋 drop around 孔雀洞雑貨舗の会、無事に終了いたしました。
当日は猛暑の中、昼の部(乾式万華鏡+マァブルスコォプ)5名+1名、夜の部(液式-乾式万華鏡)4名にご出席いただき、拙い講師にも関わらず、其其に個性的な作品を完成して下さいました。
昼の部では万華鏡の中に封じる『オブジェクト』をご持参下さる方も多くいらして、ピンクや黄緑の羽根、空色の蝶の舞うものや、貝殻の落ちるもの、紫水晶が光るもの、などなど。
夜の部ではご用意したオブジェクトを十割以上に活用して頂いて、瑪瑙が融けるようなものや、雲母が輝く品、銅線や真鍮線が迷路を作るもの、異国の切手が物語りの一片のように写る小瓶、等。
自由な発想に沢山の刺激を頂戴いたしました。
ご参加下さいました皆様、お誘い下さいましたdrop aroundさまにに心より御礼申し上げます。
kana wrote : 12:37 | comment (2)

久方振りにきらら箱さまに乾式万華鏡とテレイドスコヲプを納品いたしました。
近日中に公開・販売開始される予定です(公開・販売日時はきらら箱さまにお任せしています)。
今回は盛夏の事象をモチーフに、オブジェクト同士が重なることで生まれる瞬間の色に重点を置いて制作しております。
孔雀洞雑貨舗のきらら箱支店はこちら → きらら箱 孔雀洞雑貨舗
画像の作品は『蓮花開く音』。
kana wrote : 12:59 | comment (0)
天体航海展の展示風景を航海しました。
■孔雀洞雑貨舗 展示風景
■スパン社 展示風景
■夜間の展示風景
kana wrote : 12:30 | comment (0)

四週間に渡って開催いたしました天体航海展、無事に終了いたしました。
期間中お立ち寄り下さいました皆様、会場となったRoofオーナー&スタッフの方々、そして素晴らしい作品を展開してくださったスパン社様に心からの感謝を。
搬出後、自宅へ向かう電車の中で会社から電話が入ってしまうほど・・・本業が立て込んでおります。
展示風景などはまた後日。
kana wrote : 18:54 | comment (0)
kana wrote : 21:22 | comment (2)

◆夜の部の制作物◆
(液式-乾式万華鏡)
アルミニウムの角パイプを本体、オブジェクト(模様のもと)部分に硝子小瓶を使用した万華鏡を製作します。小瓶の一本にはオイルを入れて液式万華鏡の模様を、もう一本にはオイルを入れずに乾式万華鏡の模様をお愉しみいただきます。本体の鏡は二鏡式(模様が丸く閉じて見えます)。

◆昼の部の制作物◆
(乾式万華鏡+マァブルスコヲプ)
真鍮外装の乾式万華鏡と、古いビー玉を使用したマァブルスコヲプ、二本を制作します。両方とも三鏡式(模様が切れ目なく続きます)。マァブルスコヲプは採光部を固定しないことで、ビー玉のゆるゆるとした動きをお愉しみいただけます。

◆使用するオブジェクト◆
制作用のオブジェクトは15~20種類程度ご用意しておりますが、制作される方ご自身で封じたい<ワスレモノ>をお持ち下さることも歓迎しております。
昼の部・・・直径13mm以下、厚さ5mm以下のもの。紙やフィルムは封じた後に折れないよう補強されることをお勧めしております。また、吸湿性の高い素材、温度による軟化が予想される素材はご遠慮下さい。
夜の部・・・直径12mm以下のもの。液式用の小瓶に封じる場合には水や油に溶けない素材であり、且つ、水に沈む素材であること。乾式用の小瓶の場合には小型の切手なども丸めて封じることが可能です。
当舗では色硝子、漂着物(鹿児島で拾った貝殻、シーグラス)、鉱物(紅雲母、玉髄、瑪瑙、螢石)をご用意しております。
kana wrote : 10:51 | comment (1)
佐藤貢 個展 ~08/25(土) 茅場町 森岡書店
ルドンの黒 ~08/26(日) 渋谷 bunkamura
パルマ ~08/26(日) 上野 国立西洋美術館
---
買い物メモ
・硝子細工用のパッケージ。
・バーナーワーク用 無色の硝子(鉛)
・型取り用シリコン + 凝固剤
kana wrote : 16:51 | comment (0)

日時 2007年08月26日 昼の部 12:30~16:00 / 夜の部 17:00~20:30
会場 東京・恵比寿 atelier drop around
定員 各回4名程度
drop aroundさんの夏休み企画として万華鏡のワークショップを開催いたします。
「昼の部」では真鍮製の乾式万華鏡+細型マァブルスコヲプ
「夜の部」ではアルミニウム製の液式万華鏡本体+オブジェクト小瓶2本
を制作いたします。
※制作物の詳細画像は今週末、掲載予定です(画像は「夜の部」の液式万華鏡)。
寺子屋の詳細はdrop aroundさんのホームページをご覧下さい。
kana wrote : 12:49 | comment (0)

blues bandばかり4輪開花。開かないままの蕾、今朝はありませんでした。
蕾が開かない問題の対策。
1. 軒を越えて伸びていた蔓を解き、鉢の高さから横に沿わせることに。面積を取るけれど水上げは格段によくなります。
2. 日没後にも水遣り。今までは朝夕2回の水遣りだったのだけれど、朝夕+夜、合計3回水遣りすることに。しかし、日が暮れてからの水遣りはよくないと聞いた気もする。・・・。
3. 週末に水肥をあげること。そろそろ栄養不足の筈。
数日振りに開いたblues bandは青単色ではなくて紫と青、薄紫と水色、白単色。いずれも初めて見るパターン。本当に同じ蔓から咲いているのかと思うほど表情豊かで愉しく。
kana wrote : 12:30 | comment (0)

此処一ヶ月の間に入手した鉱物、の一部。
方解石(無色、桃色、黄色、緑色)
水晶(無色、黄色、紫色、ルチル入)
黄鉄鉱
螢石(無色、桃色、紫色、緑色)
ラブラドライト
透石膏
kana wrote : 12:36 | comment (0)

本日はZTR2005種が開花。深い赤紫地。
ZTRの鉢は赤系の種だけなのかも。
blues bandは根方の部分が病気に掛かっているせいか、金曜日から蕾が開かないまま枯れてしまっていて切ない(ベンレート系の殺菌剤を処理して感染の拡大は少し収まった模様)。
西洋朝顔は晩秋まで咲くというので、残った種を蒔いてみようかとも考えたり・・・。
kana wrote : 12:28 | comment (0)

猛烈に忙しかった先週後半、母がカビ系の病気で枯らしたヤブコウジを朝顔の鉢をblues bandの横に放置していたそうで、見事に感染してしまいました。
気付いたのは昨日の朝。鉢から50cmくらいの位置まで黒い斑点と葉の黄化が進行していて慌ててベンレート剤を噴霧。しかし一年草だと抗菌剤はあまり効果ないという人もいるので・・・どうかなあ・・・土に近い位置の茎もくったりしているし。
---
昨晩、Roofさんに追加納品して参りました。
偶然にもスパン社さんとブランコ乗りの"眼"のkotoさんとお会いして思いがけず愉しい夕食を。
奥の席に坐るとスパン社さんの箱が程好い距離で見ることができる事を発見。
お酒を頂きつつ目を上げると星座の小箱。至福です。
kana wrote : 12:37 | comment (0)